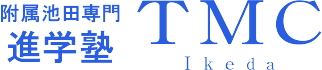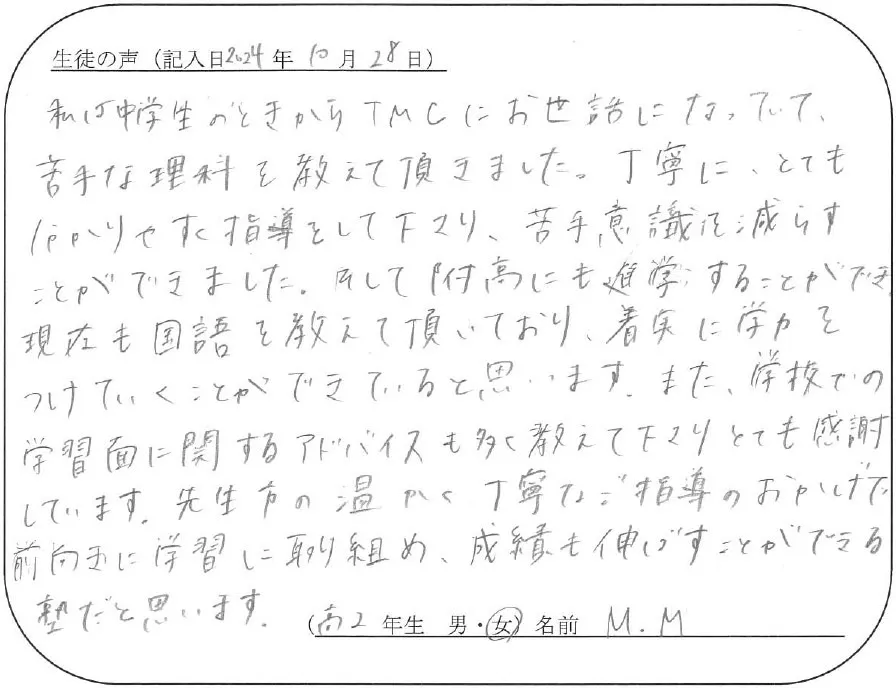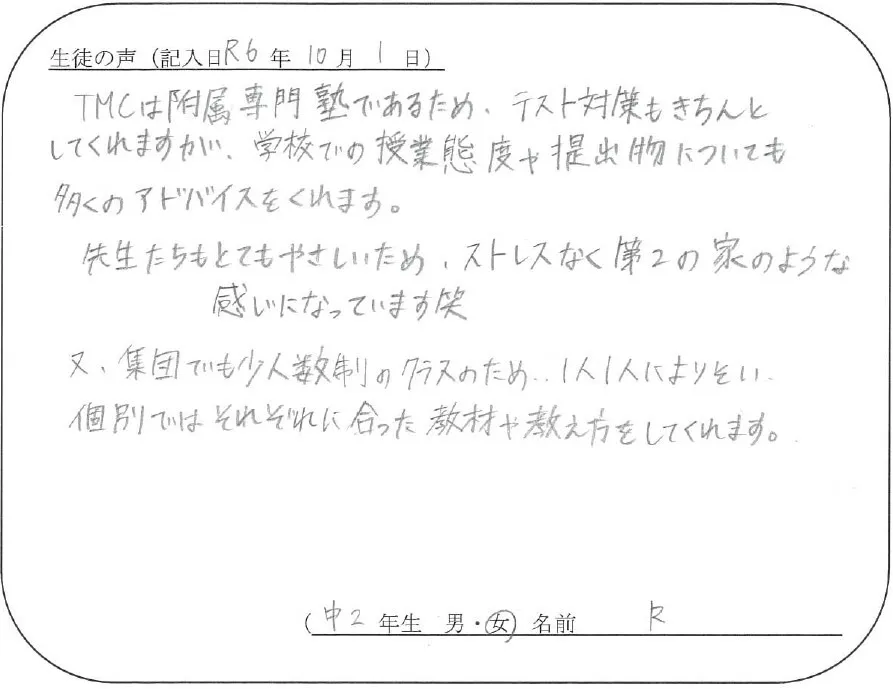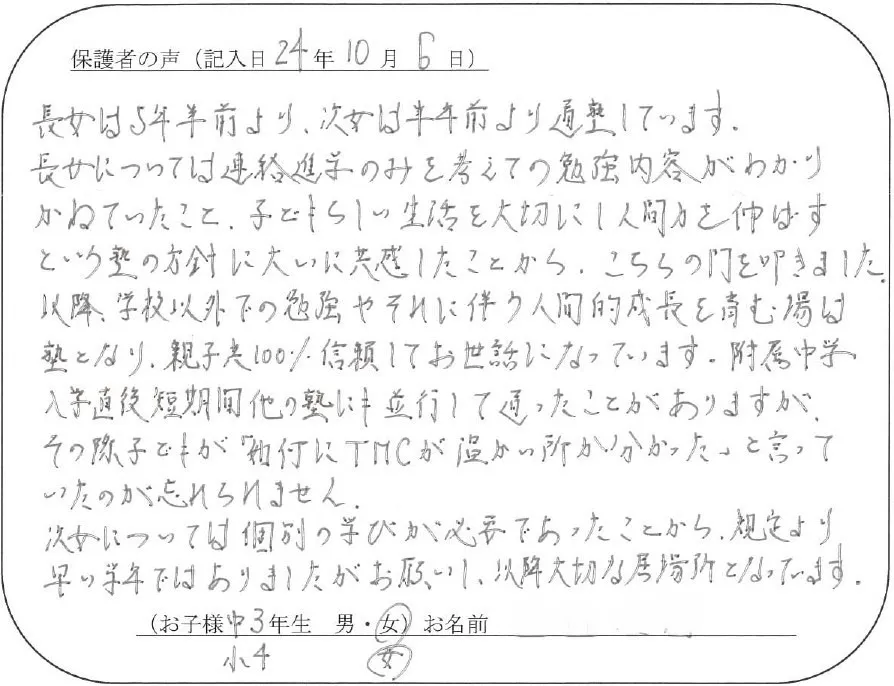塾長blog更新 『2022年度受験用『近畿の高校入試』国語 論理的文章標準問題 その2』
2021/08/12
前回からの続き。
7
- 他者あるいは「権力」からの制限や強制によってじぶんの存在が脅かされているという事態への抵抗として「自由」がリアリティを帯びる。
- けれども、「自由」はわがまま、気ままやただの放埓を正当化する恣意の自由、干渉されない自由としても用いられる。
- 差異は、脅威を感じたり、干渉されたりするのがだれかということにある。前者(①)は、本来有するはずの権利を制限される「個人」であり、後者(②)は、無制約の選択を主張するセルフィッシュな個人である。
- 「自由」という概念には「自己」という概念契機が不可欠だ。不自由とは、自己に固有の権利が認められてしかるべきものが制限されること、言いかえれば、「自己」とともにその自己に権利として属するものが侵されていることを意味する。とすれば、「自由」には(「権利」という概念契機も含まれている)。
- 自己に固有のものが何であるかについては、生命、身体、意志、身柄、所有物など、さまざまに考えられてきた。
- 「権利」としてあるかぎり、それらは正当化可能なものでなくてはならない。個人の衝動や欲望は他者のそれらと衝突し、単純には共存できないものだから、正当性の主張間にはかならず対立がおこり、正当化の主張を全うすることは困難である。したがって、根拠が認められる、普遍的に承認できるものが「権利」にはなければならない。
- そこに「自己」という景気が導入される。他者からの制限や干渉、強制や拘束を受けていないことは、裏返せば、もっぱら自己の意志にもとづいて思い、行いうること、つまりは自立的な主体であることを意味する。「自由」は「自律」と言いかえられるが、「自律」とは、自己が自己の行動の決定主体であるような個人(集団)のあり方のことだ。その意味で、「自律」は「主権性」「自己統治」「自己決定」「自己管理」「自己支配」などと言いかえられてきた。自立的な主体であるとは、「わたしがわたしの主人である」、「わたしがわたしの生の主宰者である」ということだ。
- ここで自立的=自律的というのは、わたしが他者の意志に依存しない状態にあるということだ。わたしの意志が他者のそれに依存していることは、たとえ他者によって制限を受けていなくても、じつは不自由そのものだ。「自由」とはなによりも「自由な意志」の存在を前提とし、個々人の意志の発動のうちに「自律」という回路が設定されていることが、「自由」のもっとも基本的なかたちなのだ。
〔要旨〕
「自由」という概念には「自己」という概念契機が不可欠である。「自由」は「自律」とも言いかえられるが、「自律」とは、自己が自己の行動の決定主体であるような個人(集団)のあり方のことだ。自立的な主体であるとは、「わたしがわたしの主人である」、「わたしがわたしの生の主宰者である」ということ、つまり、わたしが他者の意志に依存しない状態にあるということである。「自由」とはなによりも「自由な意志」の存在を前提とし、個々人の意志の発動のうちに「自律」という回路が設定されていることが、もっとも基本的なかたちなのだ。
8
- ルールの重要性を口にすると、「管理の強化」のような方向に誤解されがちだ。規範意識を高めるといった表現で言い換えられると、妙に道徳的な行儀の良い子どもを育てようという主張のように理解されることもある。
- ルールを大切に考えるということで、規則を増やしたり、自由の幅を少なくしたりすることを言いたいのではない。全く逆である。
- ルールは、できるだけ多くの人にできるだけ多くの自由を保障するために必要なものだ。
- なるべく多くの人が、最大限の自由を得られる目的で設定されるのがルールで、「自由」とセットになっている。
- 逆に、自由はルールがないと成立しない。
- 「何でも好き勝手やっていい」が自由だとしたら、無茶苦茶になる。ルールの共有制があるからこそ、自由が成り立つ。
- 人間が生きることの本質は自由であり、欲望の実現である。ルールは、人々が欲望を実現するための最低必要なルールなのだ。
- 欲望を百パーセント実現できなくても、一割、二割、自分の自由を我慢して、対等な立場からルールを守ることでしか、社会のメンバー全員が自由を実現することはできない。
- そして、「秩序性」は、最低限のルールをお互いが守ることの結果として出てくる。秩序正しさそのものを目的にすると、より多くの自由を我慢しなければならなくなり、息苦しさが増す。
- どんな社会でも、「盗むな、殺すな」という原則は共通して大事にされている。
- これは、社会のメンバーが生命と財産をお互いに尊重するというルールだ。
- 人を殺していいとなると、自分もいつ殺されるかわからない。「殺すな」は生命の自己保存のためのルールなのだ。
- 「盗むな」もそうだ。盗んでもいい社会では、自分の持ち物・財産がいつ盗まれるかわからない。とても不安定な状況になってしまう。だから、「盗むな、殺すな」というルールは、よほどのことがない限り、お互いのために私的なテリトリーや財産は尊重しあうという契約なのだ。
- こうした観点からは、誰かをいじめるということは、自分がいつやられるかわからないというリスキー(=危険)な状況を自分で作っていることになる。
- いじめるか、いじめられるかは、いつ逆転するかわからない。
- 無意味に人に精神的・身体的なダメージを与えないことは、自分自身の身を守り、安心して生活できることに直結している。
- 規範意識だけではいじめはなくならない。自分の身の安全を守るために、他社の身をも守るという実利主義的な考え方をある程度学校に導入したほうがよい。
- 人を殺さない、人から盗まない、というルールは、人に殺されない、人から盗まれないことを保障するために必要なものだ、という答えは、人類の歴史から出た結論なのだ。
- クラス全員が気の合う仲間どうしということは現実的には不可能だろう。大人だって、ほとんどの人は何かしらの人間関係の悩みを持っている。
- そんなとき、ムカツクからといって攻撃すれば、自分のリスクも大きくすることになる。
- だからこそ「並存性」という考え方が大事だ。お互いの存在を見ないようにするとか、距離を置くとかしかない。
- 露骨に“シカト”の態度を誇示するのも攻撃と同じ意味を帯びるので、最低限の「あいさつ」だけは欠かさず、自然に“敬遠”する。
- 要は、態度保留という真ん中の道を選ぶのだ。
〔要旨〕
自由はルールがないと成立しない。自分の欲望の一部を我慢してルールをまもることは、同時に他人から自分を守るためにも不可欠である。たとえば、すべての社会に共通する「殺すな、盗むな」は、生命の自己保存のためのルールなのだ。こうした観点からは、誰かをいじめることは、自分がいつやられるかわからないというリスキー(=危険)な状況を作っていることになる。だから、「並存性」という考え方が大事だ。お互いの存在を見ないようにするとか、距離を置くとか、要は、態度保留という真ん中の道を選ぶのだ。
9
- 「メル友を持ったニホンザル」という表題の印象。
- 周囲では、いろいろな解釈があってなかなか面白い。
- 表題にこめられた意味。第一に、サルの音声によるコミュニケーションは、携帯電話によるメールのやりとりと本質的には同一の機能を果たしている。第二に、IT社会でのコミュニ―ションは、ニホンザルのそれと変わらない。(A:つまり、)人間もメル友を持ったサルにすぎないということ。
- 実際のところ、社会の高度情報化は、人間のコミュニケーションのスタイルを根本的に変えた。それも、量の問題にとどまらず、質的にも変化が生じ、最終的に、他者との関係性の持ち方まで変えてしまった。
- 現代の日本人は、過去のような対人関係を営むことが難しくなっており、「関係できない症候群」が蔓延しているといって差し支えない。その背景は、社会の高度情報化、端的にIT化であり、それを象徴するのが、ケータイの流布である。
- ケータイを使いだすと、常に身につけて、常につながっていないと不安になる。この感覚は、私たちがコミュニケーションの媒体を共有しているという事実にもとづいて、集団としての連帯を確認するようになってきたことを示唆している。他方、メッセージは空虚化する一方だ。コミュニケーションの形態が、ニホンザルのコールによる仲間との交信と酷似したものになってきているのだ。
- 以前なら統合の象徴的役割をはたしてきた民俗や国家、会社などが、急速に影響力を失いつつある。二〇〇二年に日本でサッカーのワールドカップが開催された時には、誰もが熱に浮かれたように日本チームを応援した。
- 同じチームを応援するための熱狂、同じユニフォームを着て、声を合わすことにのみ意義があったにすぎない。それゆえ、一月後にはあとかたもなく消え去ってしまった。
- 今日の、媒体字体に依存したコミュニケーションが流布しだした端緒は、テレビの普及にある。ビジュアル系のマスメディアに幼少期からどっぷりと浸って成長した年政争は、ポスト全共闘世代にはじまる。それは学生運動が急速に停滞し、政治の無関心が議論され始めた時期だった。
- 一九九〇年代後半からの「IT革命」なるメディア変化が、事態を決定づけた。IT革命は、コミュニケーションに加わる者の要件である空間的近接性と時間的永続性をつきくずした。人々は「どかからでも」「いつでも」という利便性に魅惑された。
- 魅惑されるあまり、人々はITメディア魔法の支配から自由になった状況でのつき合いを忘れてしまった。若者は、顔を合わせて対話するほうが疲れてつらいとこぼすが、人間ひとりひとりの存在は、時間と空間の拘束を免れられない。
- 個々人は公的世界へ出て他者との交渉のなかではじめて自己実現を遂げるのである以上、空間上の近接性と時間上の持続性を欠いたコミュニケーションには、おのずと限界が生じる。その問題は、どこにいるのか確かでない相手との瞬間瞬間の交渉のなかで、相手といかに信頼関係を結んだらいいのか、そのすべを見出せないことに、もっとも先鋭的な形で浮上している。
- つまるところ、自分の損失を最低限のところで食い止める選択に走るしかない。社会の情報化によって、震源が始源的な自然状態へ戻されるという皮肉な事態がもたらされようとしている。
〔要旨〕
社会の高度情報化は、コミュニケーションのスタイルのみならず、他者との関係性の持ち方まで根本的に変えてしまった。現代の私たちは、コミュニケーション媒体の共有にもとづいて連帯を確認するようになっており、対面した上で対人関係を営むことが苦手になっている。しかし、空間上の近接性と時間上の持続性を欠いたコミュニケーションには、おのずと限界が生じる。それは、私たちがいま、どこにいるのか確かでない相手と、瞬間ごとの交渉の中で信頼関係を結ぶすべを見出せないでいることの中に現れている。社会の情報化によって、人間が始源的な自然状態へ戻るという皮肉な事態がもたらされているのだ。
10
Ⅰ
- 消費社会には、見逃すことのできない問題が多くある。このような「問題としての消費社会」を分析していく。
- 好景気を維持するためには個人消費を伸ばし続けなければならないが、生活に必要なものが行き渡れば、消費意欲は減って売り上げは伸び悩む。そこで、企業は二つの戦略を打ち出した。
- 一つは「必要な物」の品目を増やす方法。「必要」や「必需」は相対的であり、それを利用して消費は拡大された。
- 二つ目は、モデルチェンジを繰り返すなどで、「必要な物」を頻繁に買い替えさせるという方法。
Ⅱ
- このような「必要な物」の変化のメカニズムが機能することで、物があふれる社会の中で、物を手に入れても満足できずに、次々と新しいものを追い求める欲望を煽られ、常に欠乏を感じるような状態、すなわち「新しい疎外」が生まれた。これは新しい不幸ではないか。
- さらに、「物の消費から意味の消費へ」と消費のあり方が変化する。企業の広告は、その物を通じて満足することよりも、他人から羨望の眼差しを向けられることで満足することをアピールするようになる。こうして、人々の欲望は「ないと困る」から「あれば便利、快適だ」を通って、「あるとカッコいい」物を求めるようになる。
- たとえば、メディアで話題のレストランに行きたいと思う時、美味しいものを食べたいということよりも、有名でお洒落な店で食事をしたのだと周囲に言いたいという、「自分はこう見られたい」という動機が勝っている。つまり、欲望の対象が、「物そのもの」ではなく、物に付随する「意味」や「記号」に変化している。
- 消費の目的が、物そのものから満足を得ることから、「意味を消費する」ことへと変わったとき、どれほど消費しても満足できないという不幸な構造が完成する。こうした構造が確率した社会を「消費社会」と呼ぶ。
- しかも、消費への欲望は景気の浮沈を握っている。物をどれだけ手に入れても満足できない不幸な状態に人々が置かれることで経済全体が回る仕組みのなかに、私たちは置かれている。
〔要旨〕
現代では、「物の消費から意味の消費へ」と消費のあり方が変化した。欲望の対象が、「物そのもの」ではなく、物に付随する「意味」や「記号」に変化して、人々は「あるとカッコいい」物を求めるようになったのだ。だが、「意味」はいくら消費しても限界は無く、現代人は、物があふれる社会の中で、どれだけ物を手に入れても満足できずに、常に欠乏を感じるという「新しい疎外」というべき不幸な状態の中にいる。私たちは、人々を不幸な状態に置くことで経済全体が回る仕組みの中に置かれているのだ。
11
- ここで「無心」とは、「先入観をもたず、白紙で接すること」の意味だ。
- 森本哲郎は、朝日新聞の花形記者だった。
- 森本が、グアム島で生き残った横井庄一を取材したときの思い出話は、思い込みの恐ろしさを教えてくれる。
- グアムで横井庄一が住んでいたジャングルの洞窟を検分に訪れると、横井が住んでいた竹藪の岡野うえから、白い給水塔とコンクリートのアパートが見えた。
- (同行したカメラマンへの森本の指示)「あれを撮っておいてくれよ」。
- 「孤独な二十八年」というが、横井は文明のすぐそばで暮らしていたのだ、と記事を書いて送った。
- 他社に⑥の事実を書かない記者がいた。その記者は、書くと孤独のジャングル生活がぶちこわしで、面白味がなくなると思ったという。
- この体験から得た森本の結論。人間は本能的に自分の持つイメージに合わせて対象を見る。つまり、イメージに合わないものごとを、意識的・無意識的に無視したり、切り捨てたりする。
- 孤独なジャングル生活二十八年という思いにとらわれすぎると、それに合わないアパートの建物が見えても、見なかったことにして切り捨ててしまう。先入観・固定観念を持つことの恐ろしさを森本は体験から説いている。
- 現場では準備した情報にしばられず、心を白紙にして、あるがままの姿を観察することだ。
- 沢木耕太郎に「奇妙なワシ」という作品がある。
- ⑪からの引用。沢木には紋切り型の表現の中で気になって仕方がない言葉があり、それが〈ワシ〉だ。
- スポーツ紙などに、いつも「ワシ」という代名詞を使っているように書かれる選手が何人かいる。本人がワシとはいっていないようなのに、これはおかしいと沢木は思う。
- 相撲でも、本人が「ワシ」という言葉をつかっていないのに、新聞には「ワシ」と発言したことになっている。
- 沢木がボクサーの輪島功一を取材したとき、そこに横綱の輪島が訪れた。二人は「ワシ」という言葉を使わなかったのに、スポーツ紙の紙面では二人は「ワシ」を連発して会話していた。「ワシ」という代名詞は「らしさ」を装う道具であり、「らしさ」は記者の創作だ。記者は「ワシ」と言わせることで、この言葉に付着している独特な雰囲気を表そうとする。「ワシ」というアクの強い人称代名詞で表現されることで、彼らはひとつの狭いイメージに閉じ込められ、むしろ非個性的な存在にさせられてしまう。
- 白紙の心で見れば、見えなかったものが見えてくる。
- ゴキブリを見ると「汚い」と思うが、ゴキブリは本当に汚いのか。幼児にはゴキブリが汚いという思い込みがなく白紙だ。
- おかあさんに「きろいにあろうたり」という。
- ⑱の出典。亀村五郎著『幼児のつぶやきと成長』。
- この幼児は無心でゴキブリを見ているために、大人には見えないものが見えていると思う。
- ゴキブリは汚いというが、ゴキブリを汚くしている汚い場所を作っているのは人間だ。ゴキブリが汚いというよりも、汚いところをきれいにすべきだ。
- 「きれいにあろうたり」は、ゴキブリに先入観を持たず、白紙で見ているものの言葉で、無心の強みがある。
- 白紙の心でものを見るのは、そうやさしいことではない。
- 生きている以上、先入観から自由になることはできない。たとえば「野蛮人」という表現は、近代文明の枠の外で暮らす、たとえば太平洋の島々の人びとを指す、白人中心の考え方だ。
- 太平洋の島々には、それぞれの洗練された文化がある。
- ポリネシアにやってきた西洋人は、現地の固有の文化を無視して、西洋文明がそこにないというだけで、野蛮だと決めつけた。私たちもそんな白人の見方に毒されてきた。
- 近代文明を尺度にして「先進」「後進」ときめていいのかという疑問がある。文明先進国は環境後進国である場合も多い。
- 白紙で見ようとすると、いろいろなものが見えてくる。
〔要旨①〕
人間は本能的に自分の持つイメージに合わせて対象を見るため、イメージに合わないものごとを、意識的・無意識的に無視したり、切り捨てたりする。こうして形成された先入観・固定観念で対象を見ても、対象は紋切り型のイメージに閉じ込められ、その個性は覆い隠されてしまう。だが、白紙の心で見れば、見えなかったものが見えてくる。生きている以上、先入観から自由になることはできない。しかし、白紙で見ようとすることで、見えてくるものがいろいろとあるはずだ。
この文章での筆者が一番力を入れているのは、いわゆる西洋中心主義批判なんだと思います。日本人も無意識のうちに西洋中心主義にとらわれているのだ、ということ。それを強調しても良いかも。こんな感じ。
〔要旨②〕
先入観・固定観念を持って対象を見ても、対象は紋切り型のイメージに閉じ込められ、その個性は覆い隠されてしまう。例えば現代の日本人は、西洋文明を「先進」とし、それ以外を「後進」「野蛮人」と決めつける白人の見方に毒されている。そのため、太平洋の島々の文化を正当に評価することができずにいる。人は生きている以上、先入観から自由になることはできない。だが、白紙で見ようとすることで、見えてくるものがいろいろとあるはずだ。